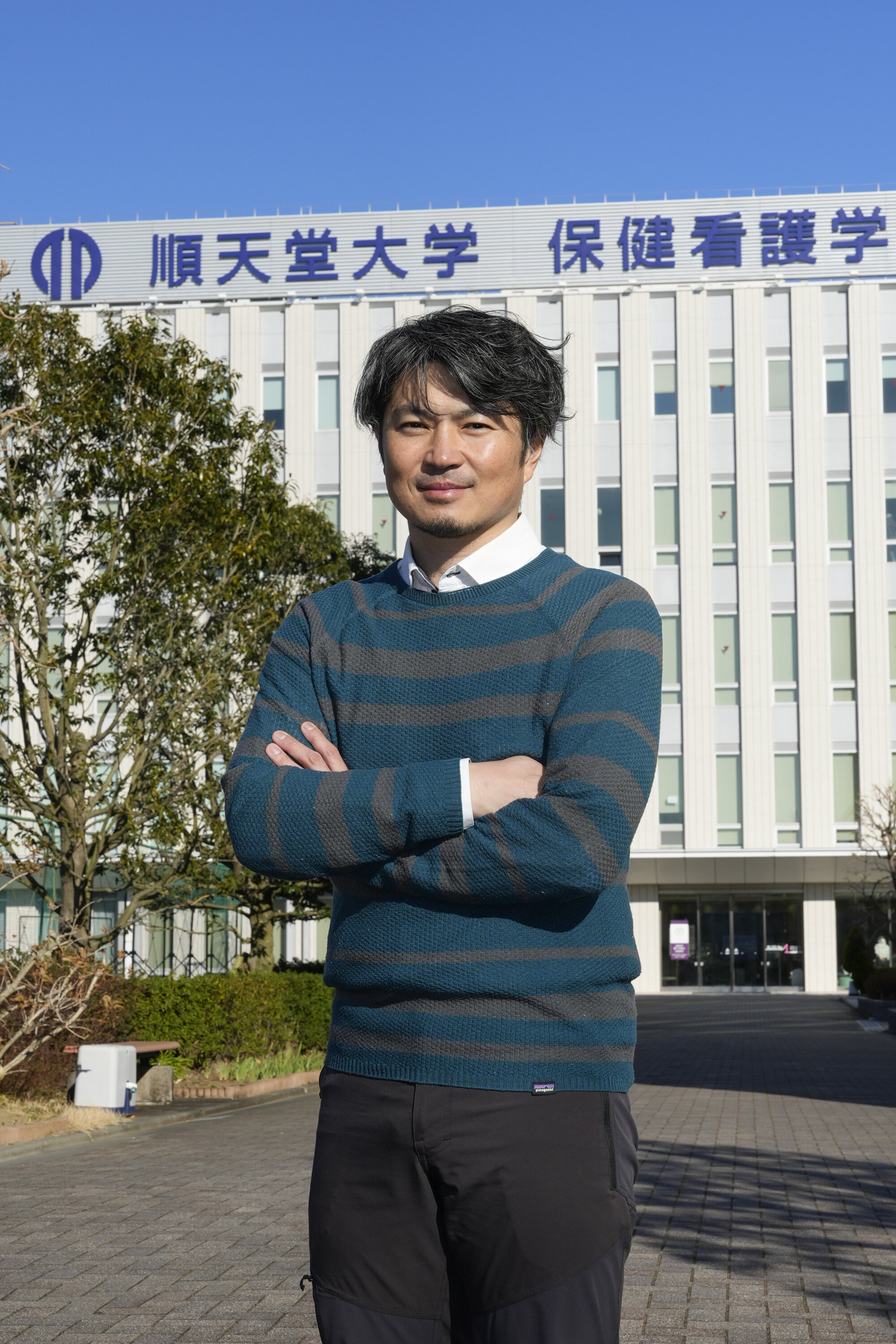PICK UP!
2025.03.28
川の中のごみ拾いから広がる可能性 ~人と地域のウェルビーイングを高める活動が全学に拡大~

順天堂大学保健看護学部(三島キャンパス)では、学生有志がスタンドアップパドルボード(SUP)を活用して三島市や伊豆地域の水辺でクリーン活動を展開しています。2024年には、10年以上続くその活動が全学的な取り組みに拡大。さまざまな学部から学生が参加し、新たに千葉県や箱根駅伝のコースの一部でも清掃活動を行いました。アウトドアスポーツと環境活動をかけ合わせたこのユニークな活動の発案者である同学部の辻川比呂斗准教授に、活動の経緯、全学での取り組みの成果、今後の展望などについてお話を聞きました。
三島キャンパスで活動がスタート
スタンドアップパドルボード(SUP)は、サーフボードよりも大きなボードに乗り、水面をパドルで漕いで進むアクティビティです。安定感があり、初心者でも乗りやすいことから、アウトドアスポーツの一つとして近年人気が高まっています。そのSUPを使って川の中でごみ拾いをする活動が保健看護学部に誕生したのは、2010年、私が担当した教養ゼミの活動がきっかけでした。WHOが掲げる健康の定義「肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態」について学ぶ中で、社会的な健康につながる身近な取り組みとして、キャンパスのそばを流れる大場川のごみ拾いを行い、その活動を継続する形で翌年、アウトドアと清掃活動を楽しむ同好会「大場川クリーンズ(DRC)」が結成されました。

当初はウェットスーツを着て直接川に入ってごみを集めたり、レジャーボートを使ったりしていたのですが、2014年ごろからSUPを利用するようになりました。SUPはアクティビティとして楽しめるのはもちろん、ボード自体が軽く運搬や取り回しがしやすい、小回りが利く、回収したごみを引き上げやすいなど、クリーン活動をする上でもさまざまなメリットがあります。そうした長所を生かして、これまでに大場川や沼津御用邸横の牛臥海岸の清掃などに取り組み、アウトドアスポーツを楽しみながら水辺の環境改善に尽力してきました。そういった活動から、最近では地元自治体である三島市から通常入ることの出来ない市立公園楽寿園にある小浜池の藻の駆除活動の要請を受けて活動しました。

千葉や箱根にも活動の場を広げて
これまでは三島キャンパスの学生による近隣地域での活動でしたが、2024年度、スポーツ庁・UNIVAS(一般社団法人大学スポーツ協会)の委託事業に採択され、SUPを体験しながら川と海のごみを拾う「SUPwell(さぷうぇる:SUP×Well-being)」と箱根駅伝コースのごみを拾う「箱根路Trash Trail Relay(TTR)」として実施することができました。全学的な取り組みに規模を拡大し、計4回のごみ拾いイベントには、8学部の学生と教職員、さらに地域住民の方など延べ155人に参加していただきました。

SUPwellは、これまでの活動エリアである三島市上岩崎公園と沼津市牛臥海岸に加え、初めてさくらキャンパスのある千葉県印西市の印旛沼でも活動しました。私自身もさくらキャンパスで4年間学び、印旛沼の環境問題は見聞きしてきたので、ようやく取り組むことができたという感覚があります。さくらキャンパスに近く、学生も日々通っている中平橋という場所で作業をしたのですが、粗大ごみを含めかなり多くのごみを回収し、今後も活動を継続する必要性を感じました。また、SUPwellのスピンオフとして企画した箱根路TTRでは、箱根駅伝目前の12月に5・6区の道路のごみを拾いました。SUPを使わない分、チームごとにごみの種類や重さ、参加者の平均歩数、心拍数を点数化して競うゲーム形式を採り、楽しく体を動かしてもらうことができました。参加した学生からは「この機会がなかったら出会えなかった他学部の学生と協力したり話せたりして、良い時間を過ごせた」といった声を聞くことができ、私自身もうれしかったです。


環境ボランティアは継続が課題
一方で、都内や千葉県内のキャンパスと静岡の移動には時間がかかり、活動時間が短くなってしまうという問題も生じました。参加者の満足度を高めるため、移動時間と活動時間のバランスをいかに取っていくかが今後の検討課題だと考えています。SUPwellとTTRは、アウトドアスポーツ、環境活動、さらに活動後の振り返り・交流をセットにしている点が大きな特徴です。活動後には、さまざまな学部から集まった学生や市民のみなさんが、地元の食材などを使ったBBQを楽しみながら交流を深め、環境問題への意識を共有しました。環境に関するボランティア活動は、いかに継続してもらうかが課題です。SUP体験やBBQといった参加者自身が幸せになれる要素によって参加のハードルを下げ、環境に対する当事者意識を育てることが、継続的な活動の土壌づくりにつながるのではないかと期待しています。

また、地元自治体との連携も活動のポイントです。大場川クリーンズは発足当初から静岡県、三島市とリバーフレンドシップ協定を結び、物品やごみ回収の支援を受けています。さらに活動を続ける中で「面白いことをしている学生がいる」と認知され、通常は立ち入ることができない場所の清掃を打診されるなど、日常的に行政とつながりを持って活動してきました。今回も、TTRではこちらが企画した道路清掃のほか、地元・箱根町からの追加提案で芦ノ湖畔も清掃しました。河川や海岸、道路のごみ回収は、行政だけでは対応しきれず、特に流れのある川の中での作業は難易度も高く、手が回らないという現状があります。この取り組みは、そうした地域や自治体の課題に対して、若い世代が集まる大学としてできる貢献の一例になったのではないかと考えています。
ウェルビーイングとシビックプライドの向上も
今回の活動は、参加者が環境活動に継続的に取り組む意識を育てることを目指すものですが、それに加えて、活動を通じて参加者自身のウェルビーイング*やシビックプライド(土地やまちへの愛着)を向上させることも目的として掲げていました。その効果を確かめるため、イベントの前後に、国際教養学部の鈴木美奈子准教授による幸福・健康感覚尺度を用いて参加者のウェルビーイングを測定。その結果、参加者のウェルビーイングが向上したことが確認されました。また、事後アンケートでは「地域への愛着度」「環境問題への関心、自然への理解」などの項目で「とてもそう思う」という回答が多く寄せられました。
*ウェルビーイング…身体的・精神的・社会的すべてにおいて良好な状態にあること。WHO憲章前文の「健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態(Well-being)にあること」から広がった考え方

今、全国各地の自治体が地域活性化に取り組んでいますが、その担い手として、私は首都圏や都市部の若い世代が地域に飛び出してほしいと願っています。若者たちが飛び出していく場所を見つける上では、単に滞在するだけでなく、ごみを拾ったり、屋根の雪下ろしをしたり、地域のためになるちょっとした活動を経験してもらうことが大切だと思っています。その場所に深く関わることによって、第二の故郷ができるかもしれません。SUPwellのように複合的な魅力を持つ活動によって、都市部の若者が地域と関わる機会として役立つ可能性は十分あると思います。

今回の実践を踏まえ、これからも三島や伊豆地域だけでなく、印旛沼や箱根路などさまざまな場所で活動する機会を作っていきたいと思っています。特に箱根は、駅伝コースのほかの区間にも範囲を広げたり、本学以外の常連校にも声を掛けたり、駅伝とからめたさまざまなアイデアも浮かんでいます。この取り組みは、アウトドアスポーツ、地域や環境への貢献、BBQでの食や交流など、いろいろな楽しみや充実感を得ながら非認知能力も高められる活動です。また、SUPで心地よく体を動かして、個人の身体や精神に良い状態をつくると同時に、ボランティア活動で社会的に良い状態をつくることもできる、まさにウェルビーイングを実現する活動と言えるのではないでしょうか。たくさんの学生や市民の方に参加していただけるような工夫を今後も取り入れていこうと思っています。