PICK UP!
2025.05.23
全身の疾患と関わる"腎臓病"の治療 ~検尿で早期発見して早期治療へ~
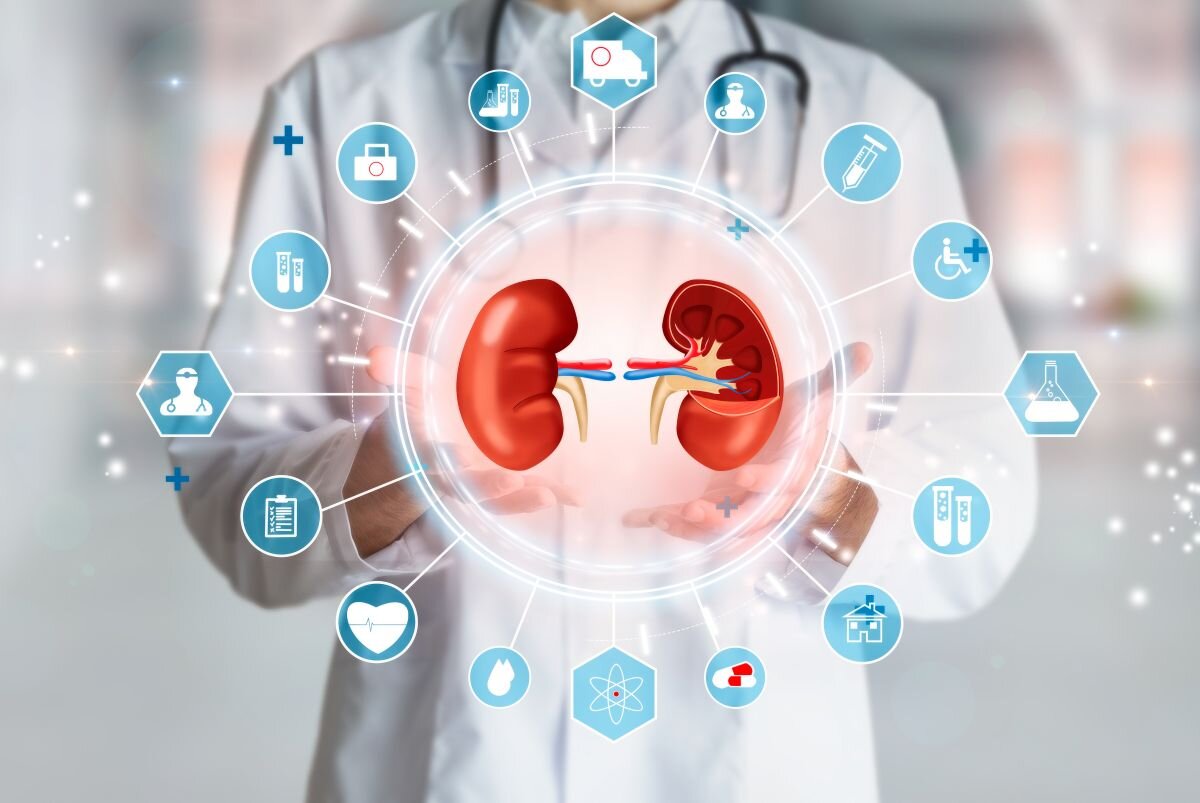
腎臓は尿を作り出して排泄するだけでなく、健康維持にとって大変重要な臓器です。腎臓病の治療では、対象臓器である腎臓に限らず、全身のあらゆる疾患を診ながら診療にあたっていかなければいけません。そのような多種多様な腎臓病の中でも糸球体腎炎(特にIgA腎症)の臨床と基礎研究において世界トップレベルの実績をあげている順天堂大学腎臓内科学 主任教授の鈴木祐介先生に、腎臓病や治療、研究の今についてお話を伺いました。
腎臓病は、全身のさまざまな疾患を診る
ヒトの腎臓は、腰の高さで背中側に左右1つずつあります。ソラマメのような形をしていて、1つの大きさは握りこぶし程度です。腎臓の主な働きは、流れ込んできた血液から老廃物をろ過して尿を作り排泄することのほか、尿量を調節して体内の水分量を一定に保つこと、ナトリウムやカリウムといった電解質の調整、ホルモンの分泌などがあります。腎臓の疾患としては、糸球体腎炎、間質性腎炎、糖尿病性腎臓病(DKD)、ネフローゼ症候群、急性腎障害(AKI)・慢性腎臓病(CKD)、水・電解質異常などがあり、高血圧、血液・腹膜透析合併症、多発性嚢胞腎、ファブリー病、遺伝性疾患なども当科の対象疾患として診療にあたっています。
腎臓は血液などの体液や電解質などをコントロールする重要な臓器なので、その機能が低下すれば全身のあらゆる臓器に影響を及ぼします。例えば腎臓の機能が低下すると塩分や水分の排泄が不十分になり血液量が増えて高血圧になります。一方で、高血圧によって腎臓への負担が増えて腎機能が悪化したり、糖尿病や膠原病、感染症、悪性腫瘍などの他の臓器の病気が原因となって腎臓病になることも少なくありません。そのため、腎・高血圧内科では腎臓以外の全身のさまざまな疾患を診て、原因となる疾患の治療をしながら腎機能に対する治療を行うことになります。
尿検査と生検*¹によって早期発見することが大切
*1生検・・・病気の診断や経過観察のために、体内の組織の一部を採取し、顕微鏡で観察する検査
日本の慢性腎臓病(CKD)推計患者数は約1480万人と言われ、20歳以上の7~8人に1人にあたる数です(2023年時点)。患者数は多いのですが、腎臓病は自覚症状がないまま進行してしまうことが多いので、定期的な検査で早期発見をすることが大切です。日本は諸外国と比べて検尿を受けやすい環境にあり、毎年6000万人が健康診断や学校検診などで検尿を受けているというデータもあります。検尿は簡易的に尿中の血液やたんぱくの有無を調べる方法で、腎臓病や腎機能の低下の早期発見につながります。また、慢性腎臓病の診断では、血液中のクレアチニン濃度を調べ、尿所見と合わせて重症度を評価します。血尿と尿たんぱくの両方が陽性だった場合は、急性・慢性腎炎などが疑われるため、腎生検を行ってより詳細な診断を行う必要があります。

しかし、自覚症状が初期にはほとんどない腎臓病は早期発見が困難です。進行して腎臓のろ過機能が正しく働かなくなり、血液中のたんぱくが大量に尿に漏れ出てしまうと、血液中のたんぱく濃度が薄くなってしまい、浮腫(むくみ)をはじめとしたさまざまな症状があらわれます。そういった症状が強く現れる一群の病気がネフローゼ症候群です。ネフローゼ症候群では、足、手、目の周りのむくみ、体重の急激な増加、だるさなどの症状があらわれます。進行すると、胸水や腹水、息苦しさ、食欲不振、腹痛なども見られ、かなりつらい状態になります。腎臓の働きが30%以下になった状態が腎不全で、ネフローゼを含む様々な原因でなります。腎不全では、体内に老廃物や水分が溜まって心不全や尿毒症など命に危険をおよぼすことがあります。
腎不全になってしまったら人工透析や腎移植も
腎臓には、細い毛細血管が毛玉のように丸まっている「糸球体」という部位が左右それぞれに約100万個、合わせて約200万個あります。糸球体は血液中の老廃物などを濾過して尿をつくり出すろ過器(フィルター)です。この糸球体はいったん壊れると、元には戻りません。そのため、進行性の腎疾患では残存した糸球体をそれ以上傷つけないようにコントロールすることがとても重要になります。腎不全になった場合の腎代替療法としては、「血液透析」「腹膜透析」「腎移植」という3種類があります。日本では9割が血液透析で、週3回、1回あたり4~5時間かけて行うのが一般的で、体内の血液を体外に取り出し、老廃物や余分な水分を取り除いてから体内に戻します。血液透析を行っている患者さんは、水分や塩分などの厳しい食事制限があることに加え、不均衡症候群*²や血圧低下、不整脈などの合併症のリスクがあります。
*2不均衡症候群・・・透析導入期にみられやすい合併症。症状は透析中から透析終了後12時間以内に起こる頭痛、吐き気、嘔吐など。

腹膜透析は、腹腔内を透析液で満たしておき、腹膜の毛細血管を介して血液中の老廃物などを透析液に移動させる方法で、定期的に透析液を新しいものに交換します。この方法は血液透析に比べて体への負担が少なく、食事制限も緩やかな反面、腹膜を劣化させるため、5~7年程度経つと機能が著しく低下してそれ以上の治療継続ができなくなります。腎移植は、血液透析、腹膜透析に変わる治療法の1つとして順天堂医院でも行っています。このような腎代替療法を選択できるようにはなりましたが、いずれもQOLへの影響が大きい治療法です。腎臓の機能が失われないで済むように、できるだけ早期に治療をしてほしいと思います。
腎臓病になってしまうと厳しい生活・栄養管理が必要
~治療中の代表的な注意点~
腎臓病により壊れてしまった腎臓は元に戻りませんから、残りの機能を温存するために血圧管理と栄養管理をしなければなりません。特に、塩分、カリウム、リン、水分の摂取について注意するよう、繰り返し栄養指導を行っています。腎臓の機能が低下するとカリウムの排出ができなくなり、血液中のカリウム値が高くなると不整脈などのリスクが高くなることから、カリウムを含む生野菜や果物の摂取は厳しく制限されます。どうしても野菜を食べたい場合は、一度煮て煮汁を全部捨ててから食べるか、少し高価ですが工場で作られているカリウムフリーのレタスなどを選ぶこともできます。また、水分とリンは血管にダメージを与える恐れがあるので、特に厳密な管理が必要です。

患者さんの中には、腎臓病の栄養管理の目的を痩せることだと誤解している人がいますが、急激に痩せると脂肪より先に水分が失われます。脱水と同じ状況となり一気に腎機能が低下してしまうので、特に腎不全の患者さんには毎日体重測定をさせ、体重管理をするようにと伝えています。最近の日本は4月、5月でも急に暑くなる日があり、腎臓病の患者さんにとって大変危険です。まだ夏の暑さに体が慣れていない状態で急に気温が高くなると、脱水となりやすいので、初夏はなるべく細目に水分をとって尿を出すように意識してもらいます。また、腎臓病になると飲めない薬もあります。特に、消炎鎮痛・解熱剤には、糸球体に血液を送る細い血管(輸入細動脈)を締めてしまうという副作用があり、血液が通らなくなって糸球体のろ過機能を一気に悪化させます。これも患者さんには十分注意するよう伝えていることです。
ろ過器である糸球体が壊れてしまう糸球体腎炎
腎臓の機能にとって極めて重要な糸球体に炎症が起きるのが、糸球体腎炎という病気です。腎臓自体に原因があって起こる原発性糸球体腎炎と、膠原病や糖尿病といった全身性疾患によって起こる二次性糸球体腎炎に分かれます。原発性糸球体腎炎にはさらにいくつもの種類があり、その中で世界的にもっとも発症頻度が高いのが「IgA腎症」です。特に日本をはじめアジア諸国で発症が多く、日本では指定難病に認定されています。日本におけるIgA腎症の推定患者数は約33000人とされていますが、実際にはそれよりはるかに多いと思われます。
IgA腎症は無症状なために発見されにくい疾患ですが、日本では多くの患者さんは健康診断などの尿検査で血尿から見つかります。病気が進行すると、血尿に加えて尿たんぱくもあらわれ、最終的には腎臓の組織を採取して顕微鏡で調べる腎生検を行って診断を行います。IgA腎症だと診断がついても、根本治療につながるような有効な治療法がなく、従来は副腎皮質ステロイド、免疫抑制薬などを用いた薬物療法、食事療法などで治療を行ってきました。ところが、近年は研究が進み、扁桃を除去する手術が有効だとわかってきました。喉の奥にある扁桃と腎臓はかなり離れた位置にあり、まるで関係ないように思えますが、以前から日本では「扁桃炎になった子どもに血尿が出て、扁桃を除去する治療をすると血尿も治まる」ということが経験的に知られており、2000年初頭、臨床研究により扁桃の除去がIgA腎症に効果があると発表され、国内で広がりました。当院では、耳鼻咽喉・頭頸科の協力のもと、全身麻酔下で両側口蓋扁桃摘出術を行ってから、腎・高血圧内科でステロイド薬を点滴投与するステロイドパルス療法を行います。
IgA腎症の発症に関わる分子を発見
順天堂大学の腎・高血圧内科は、1969年の開設以来、IgA腎症をはじめとするさまざまな糸球体腎炎の治療と研究を行ってきた実績があります。現在は、腎炎グループのほか、糖尿病腎症、腎不全、高血圧のグループがあり、より良い治療につながることを目指して基礎研究に取り組んでいます。中でもIgA腎症グループは、発症メカニズムなどの基礎的研究において世界をリードする成果を多数あげてきました。私自身も大学院生のときからIgA腎症を研究してきました。
病名にもあるIgA(免疫グロブリンA)は粘膜免疫において重要な役割を果たす抗体です。このIgAの中の一部の異常IgAが糸球体に沈着して炎症を起こします。しかし、未だに原因は完全には明らかになっておらず、治療せずに放置した人の約30~40%が末期腎不全に至ります。そんな中、私たちのグループは、異常なIgAの産生に口蓋扁桃にあるAPRILという分子の増加が影響していることを発見しました。APRILの発現を制御することで異常IgAの産生を抑えれば、IgA腎症を根本から治せる可能性があります。私たちはその治療の実現に向けて、製薬会社との共同研究により、APRILをターゲットとした治療薬の開発にも取り組んできました。これらの薬剤は国際臨床試験が進行中です。
「なぜ」を探求しながら、より良い治療法を開発
腎臓病は食事や生活を制限されることも多く、患者さんには「自分で治す」「自分も治療に参加する」という意識で治療に臨んでもらう必要があります。そのためにも、なぜ制限をしなければいけないのか、制限することで何が起きるのか、その理由までしっかり理解してもらわなければいけません。とはいえ、一度や二度口頭で説明されただけでは理解できないことも多いと思いますので、繰り返し、わかりやすく伝えるよう心掛けています。また、大学病院の役割として、治療困難な腎臓病の治療法開発に向けて、基礎研究にも注力していかなければいけません。
未だ発症原因がわかっていないIgA腎症の病態や発症・進展メカニズムの解明に努めるなど、基礎研究の成果を臨床現場にフィードバックすると同時に、臨床現場の課題をテーマに基礎研究を進める双方向のアプローチが大切です。基礎研究・臨床で「なぜ」を探求することで、患者さんに対しても「なぜ」を示すことができる医療を提供していきたいと考えています。
順天堂医院 腎・高血圧内科HP
https://hosp.juntendo.ac.jp/clinic/department/zinzo/about.html



