PICK UP!
2024.06.27
日本初のコンタクトレンズ導入から最先端のロボット手術まで ~日本の眼科医療を牽引する順天堂眼科~

順天堂眼科(医学部眼科学講座/眼科)は、白内障や角膜、緑内障、網膜疾患などあらゆる眼疾患に対応しつつ、ロボット手術や網膜イメージングなど最先技術の研究開発にも注力しています。日本で初めてコンタクトレンズを導入するなど、常に最先端治療を追求し続けてきました。今後さらなる進化を目指す順天堂眼科について、中尾新太郎 眼科学講座 主任教授に聞きました。
数々の“日本初”をもつ伝統ある順天堂眼科
――まず、順天堂眼科の特徴を教えてください。
あまり知られていないかもしれませんが、現代の眼科医療の礎を築いたといえる歴史のある眼科です。初代眼科教授(佐藤勉)は、近視や乱視に対して角膜前後面切開を行う手術を行ってきた人物で、この手術はレーシックなどその後の屈折矯正手術に大きな影響を与えました。
そのほかにもいくつもの「日本初」があります。例えば、1952年にはアメリカで開発されたコンタクトレンズを日本で最初に導入しています。また、角膜移植のためのアイバンク設立においても中心的な役割を果たし、1963年には順天堂アイバンクが日本で初めて許可されました。
――現在、順天堂眼科が強みとしているのはどんなことですか。
1つ目は、私の専門でもある網膜疾患への診療です。目の奥にあって光を受ける網膜という部位は診断も治療も難しく、視神経で脳とつながっているため移植治療ができません。そうしたことから現在も失明原因の上位を網膜硝子体疾患が占めています。一方で、iPS細胞をはじめとした先端的な医療が進んでいるのも網膜疾患で、当科でも網膜疾患の手術や診断技術の向上など、臨床と研究の両面から取り組んでいます。
もう1つが、全国に先駆けて導入しようとしているロボット支援手術です。九州大学、東京工業大学、順天堂大学、リバーフィールド株式会社により共同開発した眼内内視鏡・眼内照明保持ロボット「OQrimo®(オクリモ)」は、2023年に医療機器の承認を受け、間もなく臨床での使用をスタートします。従来の手術では眼内内視鏡や眼内照明といった手術道具を片手で持ったまま、もう片方の手で手術を行っていますが、このロボットが“第3の手”となって道具を保持するので、術者は両手を使ってより繊細な作業ができるようになります。


――眼科領域はかなり先進的な治療が行われているのですね。
網膜硝子体疾患に対する治療は手術が中心ですが、近年は、がん治療や膠原病治療などで使われている分子標的薬と呼ばれる薬が使えるようになってきました。分子標的薬は病気の発症や進行に関わるタンパク質などの分子をピンポイントに攻撃する薬で、糖尿病網膜症や加齢黄斑変性などに対する分子標的薬が登場しています。
最先端の治療法としては、遺伝子変異による網膜疾患への遺伝子治療もあります。病気の原因になっている遺伝子の代わりに正常な遺伝子を導入する治療法で、生まれつき目が見えなかった人が見えるようになったというケースも報告されています。
順天堂眼科は、遺伝子治療を行うための遺伝子パネル検査(病気の原因となる複数の遺伝子変異を調べる検査)ができる全国10施設の1つに認定されており、眼科領域の遺伝子治療の先駆けとなるべく治療や研究を進めています。
ハイレベルな研究と国際協力
――スポーツ眼科外来というユニークな外来がありますが、どのようなことをするのでしょうか。
スポーツ眼科というのは、アマチュアからプロまでさまざまなスポーツ選手の競技と目に関する相談に応じる分野で、眼科専門医である公認スポーツドクターが診療にあたっています。この分野の専門家は全国でも20人程度しかいないそうです。スポーツのポテンシャルと直結する視覚情報についてはまだ不明なことばかりですが、眼球運動の解析などを通じたハイレベルな研究も進めています。
――研究面で注力していきたいことはどんなことですか。
まず、失明原因の上位を占める網膜硝子体疾患について、ロボット手術や遺伝子治療、再生医療など、幅広いアプローチで研究を進めていきます。網膜疾患の多くは加齢にともなって発症しやすくなるため、アンチエイジングに関する研究に力を入れていきます。
もう一つの重要な研究テーマが、網膜の疾患を早期発見するための “イメージング技術”です。この分野は近年世界的に研究開発が進んでいて、私たちも光学機器メーカーと共同で高精度な眼底検査技術を研究しています。眼底検査は目の神経や血管を直接見る検査ですが、従来の手法では血管や神経の形や状態を見ることしかできません。そこで私たちは、細胞レベルで見える技術を開発し、血液がどのように血管内を流れているかまで捉えようとしています。そうすることで網膜疾患を早期に発見し、新たな治療法確立につなげることを目指します。各学部や研究センターと連携して研究を進められる順天堂は、研究する環境が整っているといえるのではないでしょうか。
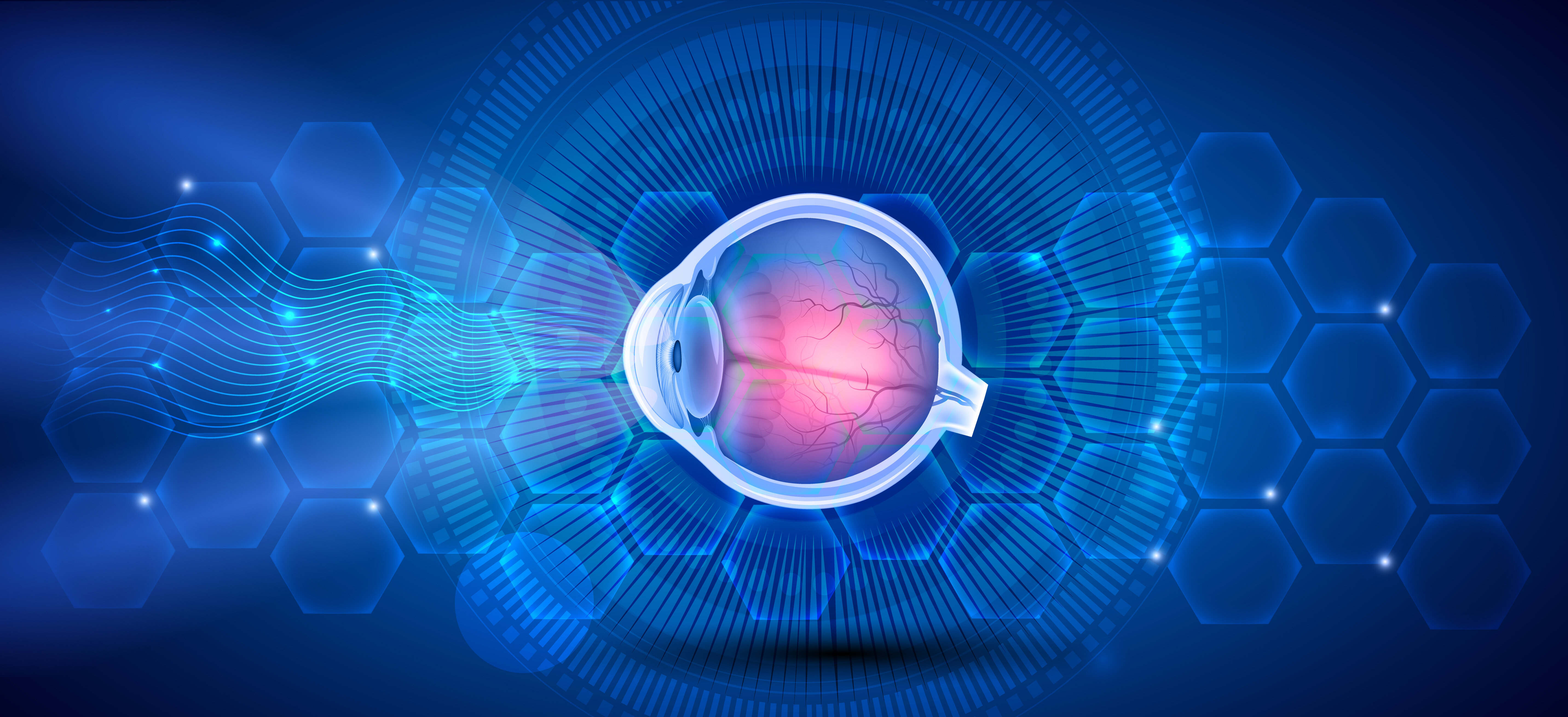
――国際協力にも取り組んでいると伺いました。
そうなんです。1980年から2016年まで、眼科学教室内にWHO指定西太平洋地区失明予防協力センターが設置されて、東南アジアの発展途上国の失明予防に取り組んできました。そもそも日本の眼科レベルは高く、世界では未だに白内障が失明原因の1位になっていますが、日本では白内障による失明はほとんどありません。そのように日本の眼科学は診断と治療レベルにおいて世界を先導する立場にあります。なので国際貢献も重要なミッションの1つだと考えています。
手術でも研究でも一流を目指せるのが眼科の魅力
――先生はなぜ眼科医になったのですか。
私が医学部を卒業した当時は白内障手術が盛んに行われるようになった時期で、若い医師でも手術を経験させてもらえることが魅力的でした。また、手術をしながら研究もできるのも眼科の良さの1つだと思っていて、学生たちにも「頑張り次第で臨床と研究の両方で一流になれる診療科」だと伝えています。
――ハーバード大学に留学したご経験がありますね。
イチロー選手がメジャーリーグに行き、中田英寿選手がセリエAに行った頃でしたので、自分も世界で勝負できるような眼科医になりたいと思ってアメリカに行きました。4年間の留学中は網膜の基礎的な研究をしていました。
この留学経験を通して得たものの中で最も大きかったのが人との出会いです。留学中に築いたネットワークは一生もので、今も世界中の友とつながっています。学生たちにも広い世界を見てほしいので、海外留学を希望する学生がいればどんどん後押ししますし、国際学会にも積極的に若い先生たちを連れていくようにしています。
若い世代は『宝』、いきいきと輝ける講座に!
――学生や若い医師たちと接するときに大事にしていることはありますか。
眼科はほかの科に比べて臨床実習の期間も短く、国家試験の問題数も少ないため、学生にとって触れる機会が少ない分野です。短い研修期間内に「眼科の魅力」を十分に伝えられるように意識しています。アメリカではあらゆる診療科の中でトップレベルの人気があり、上位10%程度しか眼科医になれないのが現状です。順天堂大学眼科も更に魅力ある診療科になるよう努めていきます。
将来の日本や医療を担う若い世代は『宝』です。若い力を潰さず、伸ばしていくことが私の役目の1つです。

――これからの眼科講座の目標はなんでしょうか。
一番は、若い人たちが夢を持てて、いきいきと輝ける講座であることです。その上で、手術でも研究でも、すべてにおいて日本トップレベルの眼科を目指していきます。具体的には、網膜硝子体の手術を中心に、全体の手術件数をさらに増やしていくことが目標です。手術件数が増えることでより多くの患者さんを治療することができますし、若い医師たちも多くの症例に触れることができます。
また、順天堂眼科を「最後の砦」として、多くの患者さんにご紹介いただけるように、紹介しやすく垣根の低い大学病院眼科を目指しています。
--最後に、順天堂眼科を目指す若い人たちにメッセージをお願いします。
網膜硝子体手術、白内障屈折手術、遺伝性眼疾患、小児眼科といった幅広い分野について、それぞれ日本トップレベルの実績をもつ眼科ですから、若い先生方には好きなことややりたいことを見つけてほしいと思います。例えば、手術の技術を磨きたい、研究で一流になりたいなど、どんなことでも構いません。眼科全般について経験を積みながら、一人ひとりが好きなことや進みたい道を見つけられるように、全力でサポートしていきます。




