PICK UP!
2025.05.12
病院内の機能回復リハビリだけでなく、地域高齢者の介護予防にも邁進
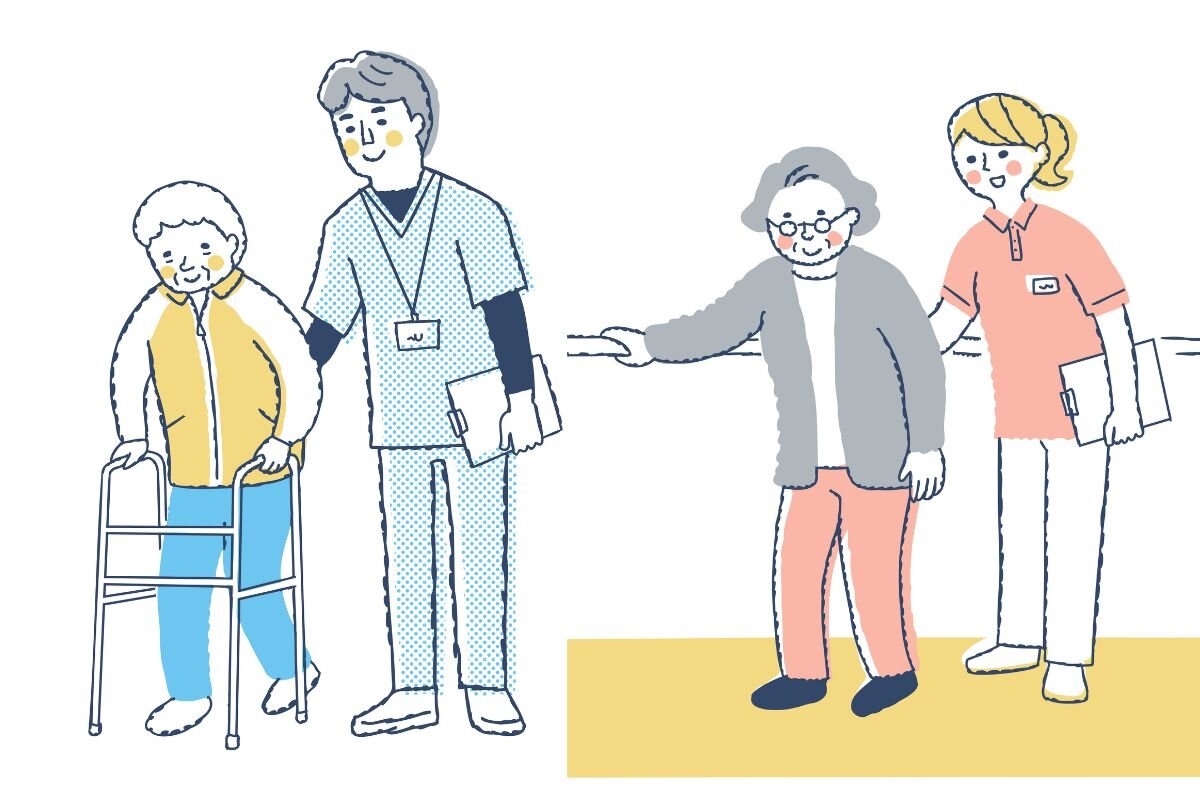
順天堂東京江東高齢者医療センター(以下:高齢者医療センター)・リハビリテーション科の國枝洋太主任は、理学療法士として脳卒中などで入院中の患者さんの脳機能を中心とした機能回復リハビリテーションを専門に行いながら、地域で暮らす高齢者の介護予防に向けた活動にも精力的に取り組んでいます。保健医療学部などともコラボレーションしながら、認知機能低下予防に邁進する國枝主任の思いや理学療法士の魅力などを語ってもらいました。
病院内では高齢者全般のリハビリテーションが専門
――國枝先生の専門分野である脳機能リハビリテーションについて教えてください。
脳卒中やパーキンソン病などの脳神経疾患などによって損傷を受けた脳の機能を維持・回復するために行うリハビリテーション(リハビリ)です。脳梗塞や脳出血が起きた後に片麻痺が出てしまったり、記憶や注意機能など認知的問題が生じる高次脳機能障害が起きることがあるので、できる限り後遺症が出ないよう社会復帰を支援します。
――具体的に、どのようなことをするのでしょうか。
高齢者医療センターで治療を受けて入院している患者さんにリハビリを行います。リハビリにあたっては、まずリハビリテーション医が患者さんの診断を行い、どの程度の負荷が可能か、血圧の目安、身体状態に応じた運動の目安などを提示(処方)します。私たち理学療法士は、その処方に沿って、患者さんの社会復帰を目指したプログラムを考えます。入院前に備わっていた能力や残存機能が少しでも低下しないように、患者さんの状態が不安定なときはベッド上で手足を動かすところから始めて、状態が改善してきたら病棟のトイレに行ったり、病棟内を移動したり、立つ練習や歩く練習を行っていきます。プログラムを作るときは、その患者さんがそれまでどのような生活を送っていたのかを知ることも大切です。一人暮らしで、自分で買い物をしていた人ならば、歩けるようにならなければ生活が成り立ちません。完全に元通りとはいかなくとも、できるだけ長い距離を歩けるように、目標を決めて入院中のリハビリを行います。また、退院後に自宅でできるリハビリプログラムも考えて、入院中からその指導をします。
病院外での地域高齢者の介護予防に向けた取り組み
――病院でのリハビリテーションのほかに、地域高齢者の介護予防に向けた取り組みを行っているそうですね。
高齢者医療センターでは、地域高齢者の健康的な暮らしを支援する活動を行っています。私たちは江東区や江東区から指定管理を受けた社会福祉法人と協働して、介護予防、特に認知機能低下予防、フレイル予防、サルコペニア予防に関連した啓発活動や機能測定会などを実施しています。認知機能低下予防のための市民向け公開セミナーなどもたびたび開催していますが、そのようなセミナーに参加する高齢者のほとんどは、重篤な病気がなく、情報収集にも積極的で、毎日の生活でも工夫している元気な方々です。なので、セミナーに来てくれた高齢者がそういった活動を続けていけるよう、背中を押すことをいつも意識しています。その上で、健康維持に役立つような医学的な情報を提供するという立場でいることを心掛けています。
――最近の知見の中で、特に知ってほしいことを教えてください。
認知症や認知機能低下を防ぐには運動や脳トレが効果的だということが知られていますが、それと同じくらい、「家から出て人と関わること」が極めて重要だということが最近のさまざまな研究で明らかになっています。私たちもその点をかなり重視しており、地域高齢者向けの認知症予防の取り組みでも、老人福祉センターやスポーツセンターといった福祉法人との協働によるさまざまな活動を行っています。それらの施設で開講している体操教室、料理教室、麻雀クラブなどさまざまなプログラムに参加することをきっかけに、家から出て、人と会い、コミュニケーションをとる機会をつくることが狙いです。ただし、重要な知見を伝えられるのは、セミナーに来てくれるような意識が高く比較的元気な高齢者ばかりなので、彼らが話を聞いて地域に戻ったときに、家から出てこない人たちに「行こうよ」と誘ってくれるリーダー的な役割を担ってほしいという思いも込めて話すようにしています。

――そのほかに地域の高齢者を対象に行っている活動はありますか。
2020年に始めた地域在住高齢者を対象とした介護予防事業では、江東区で暮らす高齢者の機能測定会を開催しています。年に1回、1人あたり90分くらいかけて、体の状態や認知機能を調べるというもので、今年度は約250人を測定しました。この事業では高齢者医療センターの理学療法士のほか、保健医療学部の教員、順天堂浦安病院の理学療法士が参加していますし、保健医療学部・理学療法学科の学生にも測定補助の学生ボランティアとして、これまでに50人以上の学生が協力して参加してくれています。
認知機能低下を予防するための研究
――研究として取り組んでいるのはどのようなことですか。
都市部で生活する高齢者に特化した、認知機能低下または回復に関連する要因の探索的研究を行っています。都市部の高齢者は、地方と比べて、車の運転をほとんどしないという特徴があり、その分歩数が多い傾向です。情報収集能力が高く、健康に対するリテラシーも高いことが、都市部ならではの特徴といえます。一方で、高齢者の二人暮らしまたは独居が多いという特徴もあります。独居はリスクと捉えることもありますが、一人暮らしだから自分で買い物に行き、家事もするというメリットがあり、独居だからこそ健康維持につながるというデータもあります。世帯構成人数が少ないから危険であるというのではなく、社会参加しているかどうかが重要なので、その点に着目した対策を行うことで、より有効なリスク評価ができると認識しています。
――研究において特に重視していることはありますか。
認知機能は長い年月をかけて低下していくので、1年後、2年後の変化に対して何が関連しているかを調べているところです。認知症の前段階である軽度認知障害(Mild Cognitive Impairment, MCI)という状態を早期に発見して対策することで、認知機能の維持もしくは回復が可能だとわかっています。65歳以上の高齢者のうち15.5%がMCIに該当するという報告もありますから、障害が発生する前の段階にある地域高齢者の認知機能、身体機能、社会参加の程度を可視化し、生活習慣を改善していくことができれば、先々の認知症発症を遅れさせて、将来的な要介護を先延ばしするチャンスが出てくると考えて研究を進めています。
重度の麻痺があっても回復できるポテンシャルがある
~理学療法士のやりがい~
――これまで理学療法士として働く中で印象に残っている患者さんはいますか。
順天堂に赴任する前に勤務していた急性期病院では、治療してある程度状態が落ち着いた患者さんはリハビリ専門病院に転院していくことが一般的でした。その中には脳卒中などで重い麻痺が残っている患者さんがいて、私は治療後リハビリをしつつ「この患者さんが自力で歩けるようになるのは難しいのではないか」と思っていました。
そういう患者さんがその後リハビリ専門病院に転院してしばらく経ってから、私のいる病院の外来にいらしたときに一人で歩いているのです。「お久しぶりです」と声を掛けてもらっても、一瞬誰だかわからないほど元気になっていました。そういうことを数多く経験しており、リハビリの効果を発揮して日常生活に戻れたのを見るとやりがいを実感できます。治療直後はどんなに重い障害があっても、回復する可能性は大いにあります。残念ながら後遺症が残ってしまう患者さんも少なくありませんが、それでも社会復帰を果たして自分の足で外来に通っているのを見ると、急性期病院でできることだけでなく、さらに先を見ながらリハビリをすることの大切さを思い知らされます。
――機能の維持・回復のためには厳しいリハビリが必要だと思いますが、精神的な負担にもなりそうですね。
患者さんの性格や障害をどれくらい受容できているかによっても違いますし、気持ちは刻々と変化していきますから、今現在患者さんがどういう気持ちでいるかを見ていかなければいけません。しかも、入院中リハビリに使える時間は、多くても1日に40分から60分でしかありませんから、それ以外の23時間を過ごす病棟の看護師さん、医師、介護助手といった人たちと情報を共有して、みんなでサポートする体制が重要になってきます。
――患者さん自身が頑張らなければいけないことも多いですよね。
頑張ればできるとは言い切れないので、そこが難しいところではありますが、患者さん自身のモチベーションはとても重要です。家に帰りたい、家族と一緒に過ごしたい、娘の結婚式に出たいなどといったモチベーションがある人は非常に強いので、私たちはそういう目標を見つけて頑張る力にしてもらいます。また、入院前や発症前の生活や障害を負う前の状態がとても大切で、そこに地域での活動が関連しています。発症前にだらしない生活をしていた人がいくらリハビリで頑張っても回復が難しくなりますし、逆に、発症前から活発に動いていた人は筋肉の状態が良く、より高い負荷を掛けられるので回復も早くなります。私はもともと病気で障害を負った人のリハビリを担当していたのでなおさら、そうなる前の早い段階から活動的な生活を送ってほしいという気持ちが強いのです。そんな気持ちで地域の高齢者に向けた活動を続けています。
元気なときから障害後まで生涯を通して考える
――今注目している分野や注力している研究はありますか。
治療のために入院しているのに、入院が認知機能低下のリスクになってしまっているという現実があります。感染症治療のために入院したら歩けなくなった、認知症になった、入院前は歩けたのに治療後退院するときは歩けなくなっているということが高齢者医療では少なくありません。そのような入院関連能力低下(Hospital Acquired Disability, HAD)を予防するための研究を始めました。HADのリスクの高い患者さんの抽出や、効果的な理学療法の実現を目指して、他職種および部署内のスタッフ教育、現状把握のためのデータ収集を行っています。

――最後に、理学療法士として大切にしていること、目標などを教えてください。
心身共に元気なときから障害を負って社会復帰するまで、私たち理学療法士はその人の生涯を通して考えていかなければいけないと痛感しています。障害を負ったときだけ、その一時点だけを見ても問題は解決しません。理学療法士として病院のリハビリ業務を行いつつ、順天堂大学の保健医療学部や関連病院、行政などと連携しながら、元気な高齢者に対する介護予防から障害を負った後の自立支援までをトータルで関わっていきたいと考えています。



