PICK UP!
2025.03.03
誰もが暮らしやすい社会にむけて~安全・安楽な医療の実現~

その専門性を活かし、「女性の健康」「看護の質」「転倒・感染予防」などの研究プロジェクトを展開している医療看護学部の飯島佐知子教授。看護師でありながら大学院で保健管理学と保健経済学を学び、経済評価について研究し、社会実装に向けた産学官連携も進んでいます。それらの研究を通じて健康で幸福な社会づくりに貢献したいという飯島教授に、それぞれのプロジェクトでの取り組みなどをご紹介していただきました。
なぜ看護師が経済評価を学ぶのか
――看護師として働いた後で経済学を学んだのはなぜですか。
看護学校を卒業後、看護師として働いていましたが、寝たきりの祖父と病気の子どもの介護のため、20代前半に仕事を辞め、それから何年間かを社会と切り離されたような状態で過ごしました。当時は介護保険制度や病児保育施設もなく、女性が介護をするものとされていたので当然のことでしたが、辛かったのは、周囲の人からは専業主婦で楽をしているように見られていることでした。人をケアするという無償の労働が世の中を支えているのに、無価値とされていることを痛感し、それらを価値付けする方法を学ぶ目的もあり大学経済学部を経て、大学院医学研究科保健経済学分野に進学しました。
大学院では保健管理学と保健経済評価を研究する先生のもとで、症例別の病院の原価計算の方法を開発し、大腸がん手術症例の手術部位感染予防対策の費用効果分析などの研究をしました。感染管理看護師や医師が協力して無駄をなくして適切な感染予防対策を実施することにより、感染率が減り、患者さんが早く退院して病院の原価や医療費を減らせることが明らかになりました。この研究は、女性の健康の経済評価、看護の質の評価や転倒予防などの研究につながっています。2017年には、厚生労働省科研費により「女性の健康の社会経済学的評価」という調査を行いました。

――「女性の健康の社会経済学的評価」ではどのようなことを調査したのでしょうか。
女性特有の健康課題を社会的・経済的側面から包括的に捉えるための調査を行いました。その結果、1年間の医療費の総額は男性よりも女性のほうが多く、その中でも女性特有の疾患では、医療費よりも勤労ができなくなることで生じる生産性損失が大きいことがわかりました。次に、企業、市町村、都道府県が女性の健康に対してどのような支援を行っているかを調査したところ、ほとんどの事業所、市町村、都道府県において広報や教育のための予算や人材が不足しており、十分な取り組みが困難な状況にあることがわかりました。そのような中でも、熱心かつ積極的な支援事業を行っている事業所、市町村、都道府県の事例集を作成し、厚生労働省のHPで公開しています。
厚生労働省HP:https://www.smartlife.mhlw.go.jp/event/womens_health/2020/theme06
子宮頸がん予防のためのDXシステムを構築
――現在取り組んでいるプロジェクトについて教えてください。
今注力しているプロジェクトの1つが、「DXを活用した地域連携による包括的な子宮頸がんの予防」です。子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)に感染することで発症するがんなので、性的接触をする前にHPVワクチンにより感染を予防することや、定期的な検診で、がんになる前に見つけて治療することが肝要です。欧米では対策が進み子宮頸がんの死亡数が年々減っているのですが、日本では思うように進んでいません。子宮頸がんワクチンの累積接種率は43.1%と、WHO(世界保健機構)の目標値の90%の半分以下ですし、子宮頸がん検診受診率は20~29歳が27.0%、30~69歳が45.9%と、OECD(経済協力開発機構)加盟国平均値の61.4%を大きく下回っています。
現在、日本では毎年約1万人の女性が子宮頸がん・上皮内がんと診断されており、その2人に1人が妊娠・出産年齢である20~30代の若い女性です。そして、死亡者数は約3000ですが、そのような実態もほとんど知られていません。
――日本の子宮頸がん予防対策が進まないのはなぜでしょうか。
HPVワクチンについては、接種対象者の保護者に情報が届いていないことが要因の一つだと思います。このため、市町村も自宅に接種案内を送っており、厚生労働者や日本医師会や様々な団体がホームページや動画サイト、SNSなどでHPVワクチンや子宮頸がん検診について広報しています。それでも、関心のない方の目には留まらないので、学校などで保護者と接種対象者が一緒に学べるようなわかりやすい情報を手元に届ける必要があると思います。

また、20歳代の方の子宮頸がん受診率が低いのは、子宮頸がんが若い人に多いことやの検診の必要性が伝わっていないためだと思います。住民票のある市区町村は、制度として、子宮頸がんのワクチン接種や定期健診についてのお知らせを郵送しており、一部の市町村は20歳の人には検診の無料券を郵送しています。しかし、2022年に私たちが20歳代の日本人女性1500人を対象に行った質問紙調査によると、半数近くが市区町村のお知らせを「見たことがない」「わからない」と回答されていました。そもそも自分が受診対象であることを知らなかった人も少なくありませんでした。 その理由として、20歳代の若者は大学入学のために実家を出て一人暮らしをしたり、就職のために転居する人は多いのですが、若者の6割が住民票を現住所に移していないという実態にそぐわない制度に問題があると思います。また、未受診の理由としては、「検査が怖い」「費用が心配」「時間がない」「受診方法がわからない」「恥ずかしい」などの理由を挙げる回答者が多かったのです。自分が受診対象であることを知ったとしても、交通費をかけて実家や前住所に受診券や無料券を取りに行き、その市区町村の医療機関で受診する若者は少ないと思われますので、職場や学校で受診券を配布していつでもどこでも受けられる制度が必要だと考えます。この調査では、どうすれば「受診したい」と思えるかという質問もしています。学会や厚生労働省などのホームページの情報提供については見ていないためか、受診したいとは思わないようでした。それよりも家族、友人、学校、職場などの身近な人からの勧めがある場合は受診したいという思う人の割合が高かったです。こうした調査結果を踏まえて、私たちはITベンチャー企業数社とともに、個別の情報提供を行って受診行動に結びつける仕組みを作ろうとしています。
患者さん視点で看護の質をきちんと評価したい
――子宮頸がん予防以外で注力していることはなんですか。
医療の質の評価というテーマでは、看護の質を評価する尺度を作ろうとしています。これまでは患者さんの満足度といった評価方法しかなく、患者さんの個別性に配慮して看護ケアを提供するするという看護師の仕事の過程について評価されていませんでした。 そこで私たちは、フィンランドのトゥルク大学看護学部の協力を得て、「患者さんの個別性を尊重した看護ケアの評価尺度」の日本語版を開発しました(2017-2020年)。この尺度を使って、日本の病院に入退院した日本人と外国人の患者さんを対象に行った質問紙調査では、日本病院の看護師のケアの質が高く評価されているとわかるとともに、外国人患者さんからの評価が日本人患者さんの評価よりも高いということが明らかになりました。

――外国人と日本人では日本の看護師の評価に差があるのですね。
海外と日本の看護師では、ベッドサイドで過ごす時間が違うのではないかと思います。回答してくれた外国人患者の国籍は中国、フィリピン、米国などでしたが、それらの国の看護師の業務は、血圧や体温などの測定やアセスメント、薬の配布、検査や治療の補助や身体的な処置が中心ですが、日本の看護師は身体清拭や食事介助などの体のケアのほか、不安や悩み事を聞くなど心のケアにもかなりの時間を費やします。そういったところが外国人患者さんに評価されたのではないでしょうか。ベッドサイドでのケアに加えて、病気の予防や健康指導など、入院中や生活の場における患者さんの安全・安楽*1を図ることも看護師の主要な仕事です。ただ、それらの活動はあまり評価されていないと感じることがありますが、正しく評価され、その評価に基づいてより良い看護や医療が実現されることを目指しています。また、看護に関連した評価として、外来での患者さんの経験を評価する尺度の開発や転倒予防対策の研究を進めています。
*1安楽・・・不安や苦痛がなく,快く自分らしく過ごしていただくこと。
転倒を防いで、安全・安楽な医療を実現
――転倒・感染予防の取り組みについても教えてください。
2007年に、電子化された転倒予防アセスメントツールの転倒リスク項目を入力していくと、患者の転倒リスクに応じて自動的に標準的な予防策が提案されるシステムを開発しました。このツールは愛知県の公立陶生病院で開発して導入したところ、転倒による大腿骨骨折など、外傷の件数が導入前よりも減って、外傷の治療に要する医療費を1人あたりで約50万円削減することができました。このシステムの一部は順天堂医院でも使用されています。転倒予防の研究は現在も大学院生達と継続しており、教育用のプログラムなども開発しています。今後はこれらをパッケージ化して、安全管理や看護の質管理のためのツールとして活用できればと考えています。
――転倒予防のシステムは、かなり先進的なもののようですね。
システムそのものもそうですが、6万件におよぶ導入後のデータを分析した結果がとても興味深いものでした。その分析によると、転倒予防についてはベッドの柵やアラームなどの物理的対策による効果は小さく、患者さんの状態から看護師が患者さんの行動を予測してベッドサイドにうかがい動作介助を行うなどの人的対策の方が大きいとわかりました。経験が浅い看護師にとって予測が難しい事例もありますが、アセスメントツールを導入することで注意すべきポイントが明らかになり対策がとりやすくなるというメリットがあります。国による転倒リスクの違いもユニークでした。例えば、日本人の患者さんは「看護師さんが忙しそうだから迷惑をかけたくない」「入院中でもできるだけ自分のことは自分でやりたい」という理由から、なかなかナースコールを押さない患者さんもいます。そのために自分で動いて転倒が起きてしまうのですが、これは外国ではあまり見られない転倒リスクです。一方、高身長な人が多い国では、下半身の骨格が長く重心の位置が高いため、身長の低いアジア人よりも転倒率が高い傾向にあります。また、新しいがん化学療法剤の導入が転倒リスクになるなど、時期によってもリスク要因は変わりますので、数年おきにアセスメントツールの内容を見直し、ブラッシュアップしていくことが必要だと考えています。
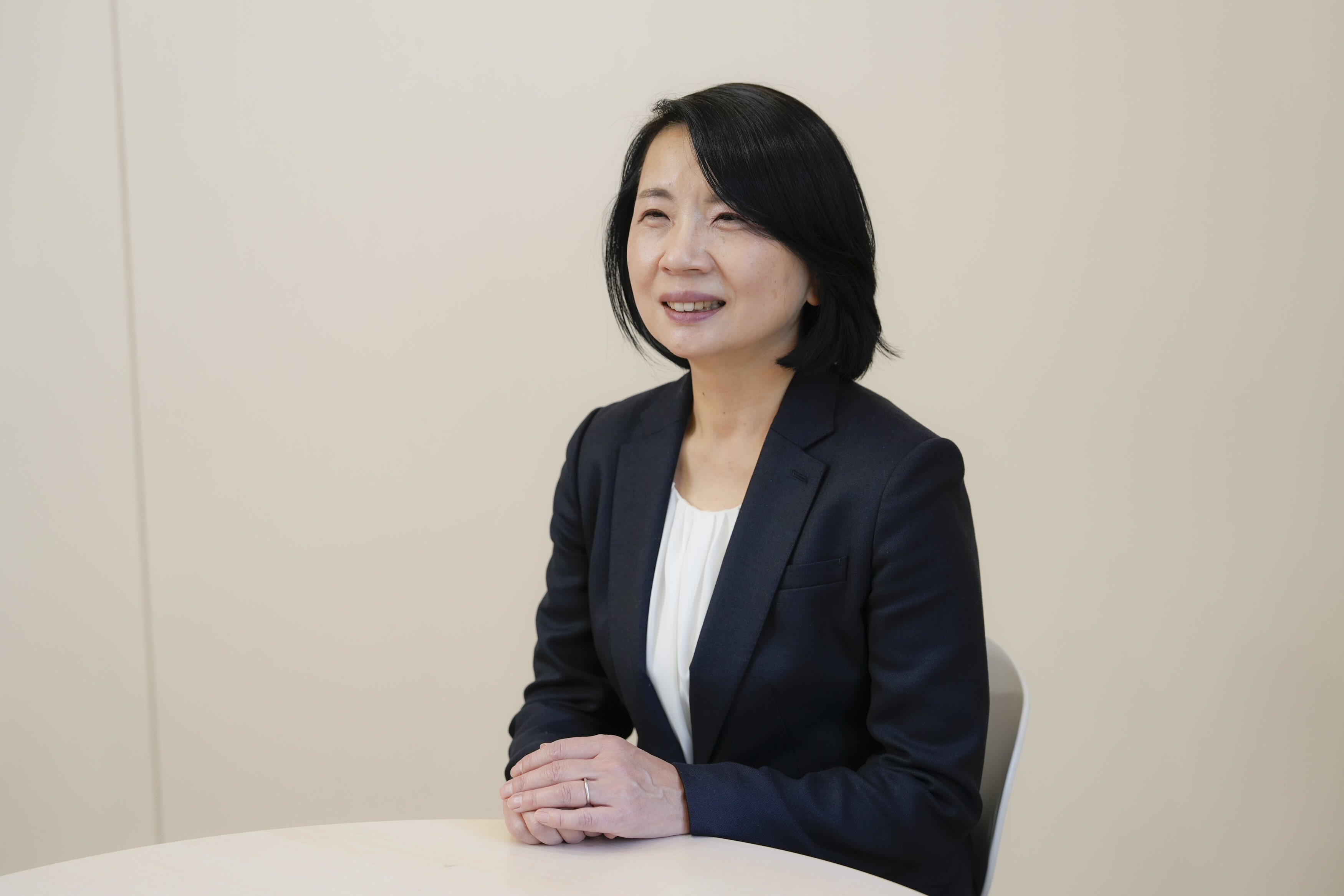
――最後に、今後に向けた目標など教えてください。
昔は「どうして看護師が経済評価をする必要があるの?」と言われることもありましたが、今はなくなりました。介護保険制度や在宅医療などの仕組みもあり、良い時代になってきたと感じています。しかし、女性の健康課題や、医療の安全を担う看護リソースの不足など、問題は山積みです。私は、市区町村や医療機関、学校、職場が協働できるDXシステムを開発することでそれらの社会問題を解消し、誰もが生涯にわたり健康に社会生活を送り、望む人が子どもを産み、幸せに暮らせる社会の構築に貢献したいと考えております。



