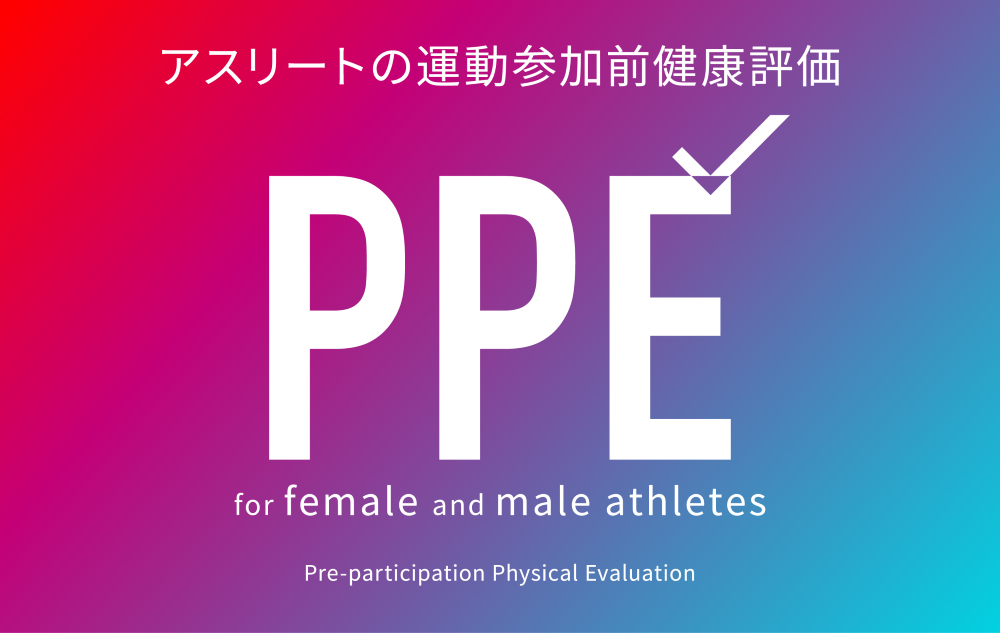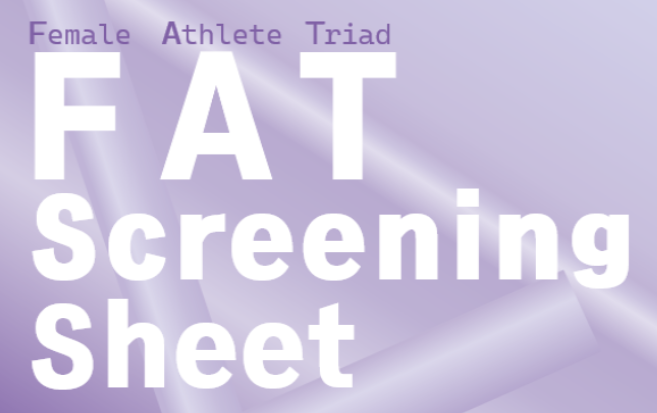PICK UP!
2025.11.14
すべての女性がスポーツで輝くために「女性スポーツ研究センター」

女性アスリートに関する研究機関として順天堂大学に設立され、2024年に10周年を迎えた「女性スポーツ研究センター」。小中高校生からトップアスリート、高齢女性まで、ライフステージを通じた女性のスポーツと健康を支える研究成果は、多様なプロダクトとして広く利用され、スポーツ健康科学部の教育においても大きな役割を果たしています。その功績が評価され、2023年度には秩父宮記念スポーツ医・科学賞奨励賞を受賞しました。これまでの研究・普及活動の成果、女性スポーツにおける今日的課題、学生教育への展開などについて、副センター長の鯉川なつえ教授と三倉茜助教に聞きました。
女性スポーツの「3つの課題」
(鯉川先生)女性スポーツ研究センターは2014年8月、女性アスリートのコンディショニングや女性スポーツの環境改善を目指す国内初の研究支援拠点として設立されました。同年10月には、国内初の「女性アスリート外来」が順天堂大学医学部附属順天堂医院、浦安病院に開設されています。2014年は、なでしこジャパンがW杯で優勝(2011年)、東京オリンピックの開催が決定(2013年)し、これから女性スポーツの機運が高まっていくというタイミングでした。2019年以降は、スポーツ健康科学と医学の領域から、アスリートのみならず「女性とスポーツ」に関する包括的な研究にも取り組み、その成果に基づく実用的なプロダクトを数多く社会に提供しています。2024年11月には設立10周年を記念して国際シンポジウムも開催しました。

(三倉先生)女性スポーツの課題は、大きく3つに分類されます。女性特有の月経、妊娠出産、閉経などに伴う「身体・生理的課題」、自分の体へのマイナスイメージや“女の子はおしとやかに”といった育て方がスポーツ参加を阻害する「心理・社会的課題」、女性のリーダーやコーチの不足や女性チームの不足などの「組織・環境的課題」です。この10年間で、女性アスリートの無月経、妊娠出産後の競技継続といった問題には社会的注目が集まり、「身体・生理的課題」に関するサポートは充実してきました。一方で、より課題がクリアに見えてきたのは「心理・社会的課題」「組織・環境的課題」の2つです。身体・生理的課題は、その解決がメダル獲得やパフォーマンス向上という分かりやすい成果に繋がるため対策が進んだ、という側面があります。しかし、スポーツ組織の女性リーダーや女性コーチが増えることのメリットは目に見えにくく、女性がリーダーにアクセスしにくい日本社会の文化的構造的問題とも絡み合って、対応が後回しにされてきました。ただ、近年は社会のジェンダー意識が変わりはじめ、組織的課題も少しずつ動きつつあるように思います。

部活動をする女子中高生をさまざまなツールで応援
~男性指導者に向けても発信~
(鯉川先生)女性スポーツ研究センターの特徴の一つに、研究成果に基づいて開発されたさまざまなツールやコンテンツを世に送り出している点が挙げられます。特に力を入れているのが、部活動をしている女子中高生に向けた発信です。2024年に公開した「Girls in Sport」は、女性アスリートに多く起こる身体生理的課題を予防するための情報を伝えるウェブサイトで、当事者である女子中高生だけでなく、部活動の指導者、養護教諭、かかりつけ医などの関係者に向けて、身体の状態を正しく知るための動画や、指導に役立つマニュアルを公開しています。
ほかにも、コンディションをセルフチェックできるツールとして、毎日の身体の状態と練習スケジュールや振り返りを1年間記録できる「女性アスリートダイアリー」、運動に参加する前後の健康状態を評価するオンラインツール「PPE for female and male athletes」などをリリースしています。PPEは2021年に女性アスリート用に開発・提供したものですが、「男性版もほしい」という要望を受け、2025年10月に男性アスリート用を追加で開発しました。
女性アスリートの身体生理的課題への理解が広がる中、女性に月経や体調について聞くことを「セクハラと受け取られるのではないか」とためらう男性指導者もいるといいます。そうした場面で活用できるのが「FATスクリーニングシート」です。FATとは女性アスリートが陥りやすい3主徴(エネルギー不足、視床下部性無月経、骨粗しょう症)のことで、28の質問に答えることでFATの危険性をセルフチェックできます。男性の先生には、『本人に話しにくい時は、このシートを渡して保健室の先生に回収や対応をお願いする、という使い方もできますよ』とアドバイスしています。
ジュニア世代へのサポートが未来を拓く
(三倉先生)また、中学・高校のスポーツ系部活をしている女の子を対象とした研究に、Doveとナイキによる世界的プロジェクト「ボディ・コンフィデント・スポーツ」への参画があります。このプロジェクトは、10代の女の子がボディ・イメージ(自分の身体に対するイメージ)の悩みからスポーツをやめてしまうことがないよう支援する世界規模の取り組みで、女の子に自分の身体に自信をつけてもらう対面研修と、指導者向けのeラーニングを開発し、ウェブ上で公開しています。女性スポーツ研究センターは、日本における調査や日本語サイトの監修・翻訳を担当しました。思春期にボディ・イメージが低下し、スポーツから離れてしまう女の子は少なくありません。ボディ・コンフィデント・スポーツは、女の子が自分の良いところに目を向けられるようサポートすると同時に、指導者や保護者がボディ・トーク(身体に関することを話題にすること)の弊害などを学び、女の子が安心してスポーツに参加できる環境をつくるためのものです。

(鯉川先生)スポーツは女性の人生に大きな力になります。しかし、10代女子がさまざまな理由でスポーツを止めてしまうことが問題になっています。その割合は男子の2倍ともいわれています。女性スポーツがこれからさらに発展するためには、女子中高生はもちろん、指導者、保護者など彼女たちを支えるアントラージュ(選手を取り巻く関係者)が正しい知識を持つことは非常に重要だと考えています。女性スポーツ研究センターのジュニア世代へのアプローチは、今スポーツに励む女子中高生を支えるとともに、将来にわたる女性の心身の健康と幸福を育てる取り組みでもあります。
学びでつながる「女性リーダーアカデミー」
(三倉先生)研究成果は、女性スポーツを支える専門人材の育成にも活かされています。女性スポーツ研究センター設立の翌年にスタートした「女性リーダーアカデミー」は、スポーツ界でリーダーやコーチを目指す女性を対象に、科学的研究に基づいた教育やトレーニングプログラムを提供し、これまでに335名の修了生を輩出しています。参加者は、現役の女性コーチや将来指導者を目指す女性アスリート、さらに理学療法士、管理栄養士、スポーツ組織の役員・職員などさまざまです。中学・高校の部活の指導者から日本代表レベルのコーチまで、バラエティ豊かな修了生たちは、現在、全国のスポーツ現場で活躍しています。私もアカデミー修了生の一人です。
アカデミーは、学びだけでなく、ネットワーキングの面でもとても意味のある場になっています。女性のコーチやスタッフは人数が少なくあちこちに点在しているので、なかなか横の繋がりが持てないことが現状です。アカデミーを機に、意外に近くにいたんだと気付いたり、励まし合ったり、こういう時どうしてますか?と情報交換ができたりします。『このアカデミーに背中を押されて、コーチの職に就くことにしました』という話も伺い、人生を変えるような場になっていると感じます。

(鯉川先生)修了生のつながりは強く、最近ではトレーナー、理学療法士、管理栄養士の修了生が集まり、産後の女性をサポートする会社を起業したという例もあります。さらに、アカデミー修了後、学び直しのために順天堂大学の大学院に入学するケースも珍しくありません。修了生の中で、代表レベルで活躍する女性コーチや、組織のリーダーになる女性も少しずつ増えています。その人たちがロールモデルとなり、次の世代に繋げることで、女性スポーツの環境に良い循環が生まれることを期待しています。
スポーツ健康科学部で広がる学びと理解
(鯉川先生)女性スポーツ研究センターの研究成果をはじめ、国内外の女性スポーツに関する最新の情報は、スポーツ健康科学部の授業に積極的に取り入れられています。スポーツ健康科学部には中学・高校の保健体育教員を目指す学生が多く、月経など女性アスリートの身体生理的課題についても、大学に入るまでに深く教わる機会がないこともあり、男子学生の方が真剣に授業を聞いています。
(三倉先生)さらに、身体・生理的な分野以外でも、スポーツマネジメントやスポーツ社会学など、さまざまな分野で「女性」を切り口に卒業論文や修士論文を書く学生が増えています。例えば、女性スポーツの観戦者にスポットを当てたり、スポーツボランティアの女性を取り上げたり、研究トピックがかなり広がっています。学生の女性スポーツに対するイメージがより多面的になり、さまざまな角度から研究できることが浸透してきました。
(鯉川先生)学ぶことで、これまで当たり前のように後回しにされてきた女性の課題に対して『それっておかしくない?』と疑問を持つ視点が生まれます。その気づきこそが、現状を変え、スポーツの世界をより良い方向へ導く力になります。最近、スポーツ健康科学部では、女性とスポーツに関するディスカッションが活発に交わされるようになってきています。

女性スポーツ研究センターはこれからも、学内や国内での女性スポーツ研究・啓発活動にとどまらず、グローバル規模での活動に積極的に参画していきます。特にアジアの女性の健康とスポーツ参加促進に取り組み、今後、新たな研究や普及啓発活動を展開する予定です。また、スポーツ健康科学部の教育を通じて、最先端の女性スポーツ科学の知見を学生に伝え、社会やスポーツ現場に学びを還元できるスキルを持った人材を送り出し、スポーツをするすべての女性をサポートしていきます。

女性スポーツ研究センターHP